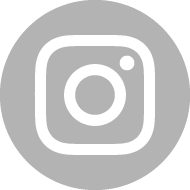振袖BLOG
振袖のお役立ち情報を発信中
【夏の風物詩】浴衣について知ろう☆浴衣っていつからあるんだろう?着物と何が違うの?
日本の夏の風物詩の一つに浴衣がありますね。
今年も、夏祭りや花火大会に浴衣を着ていこうと考えている方も多いのではないでしょうか。
そんな浴衣について、ふと「いつからあるんだろう?」「着物とどう違うんだろう?」
などと思ったことはありませんか?
今回は、そんな浴衣について歴史や着物との違いなどをご紹介します。
☆浴衣の着付けや帯アレンジなどお役立ち情報満載☆
浴衣についてのブログはこちら
☆袴の身のこなしや当日の持ち物などお役立ち情報がいっぱい☆
卒業式関連のグログはこちら
☆振袖専門館花舎の振袖コレクションはこちらから☆
色別やジャンル別でたくさん載ってます
↓↓↓↓↓↓
https://kasya.jp/furisode/
☆花舎の前撮りインスタグラムはこちら☆

Contents
浴衣の歴史
浴衣の原型は、平安時代にさかのぼり、貴族が風呂に入るときに肌をさらさないように着用した、湯帷子(ゆかたびら)という着物です。当時は、狭い部屋に蒸気を充満させ体を蒸らして汚れを落とす蒸し風呂だったため、現代のサウナのようなスタイルだったのでしょうか、麻織物で作られた湯帷子を着て入っていました。
時代は進み、仏教の浸透とともに現代のようなお湯につかる入浴法が一般化されていきました。江戸時代に浴衣は湯上りに着るものとなり、庶民の間に広まっていきました。素材も、麻に代わって木綿が普及し始め、吸水性も高いことから綿織物が着物に用いられるようになり、現代の浴衣につながっていきました。
江戸時代中期には柄に趣向が凝らされるようになり、“湯上りに着るもの”から家の中で着るような家庭着となっていきました。この頃に袖の形も、開放的な広袖の形(袖口の下を縫い合わさない袖)から通常の着物の袖の形になっていったようです。そして、盆踊りや風流踊りが流行するころに、歌舞伎役者が着た浴衣が流行ったり、華やかな浴衣が庶民の間で着られるようになっていきました。
人前で着るものとして扱われなかった浴衣が、男女ともに外出にも着るようになったのは明治中期以降です。それは、天保の改革により、庶民が絹を着ることが禁止されたことや、明治時代に入り注染(ちゅうせん)という新しい染色技術が導入され、丈夫で長持ちするようになったりしたことが大きな要因でしょう。
近年では、梅雨が明けるころ七夕や盆踊り、花火大会、お盆など浴衣を着る方を見かけるようになりました。また、観光地では海外からの観光客が浴衣をレンタルして楽しんでいる姿をよく目にするようになりましたね。着こなしも多様になり、草履ではなく靴や、サンダルを履いたり、洋服の上に浴衣を着たり、伝統にとらわれないスタイルで楽しむ方も増えていますね。
浴衣と着物の違い
浴衣と着物は見た目はそっくりですが、違いがたくさんあります。
素材の違い
まずは素材です。
浴衣に使われている素材は、綿か麻が多いです。
綿や麻は吸水性が高く、風通しが良いので夏に着る浴衣には最適な素材ですね。
一方着物は、絹やウールなどの天然素材が昔から使われていましたが、現在では、手入れしやすいポリエステルなどの化学繊維を使ったものも出てきました。
絹は、綿や麻と同じように吸水性と通気性が良いことに加え、吸湿性と保温性にも優れています。そのため、夏場は汗を吸収しても素早く湿気を放出することができ、冬場になると、薄くても温かさを保てます。軽くて丈夫なことも特徴です。
仕立ての違い
仕立て方は、浴衣も着物の一種なので、形は同じに見えますね。
しかし、浴衣は単衣(ひとえ)仕立てと言って裏地がなく生地一枚の仕立てです。これは、夏の着物の仕立て方と同じです。夏の時期は、通常の仕立ての着物では暑すぎるので、薄い生地で単衣仕立てになっています。5月ごろから9月ごろまでの期間に着る着物は単衣仕立てです。
通常の着物は裏地を付けて生地が二重になるように仕立てる袷(あわせ)仕立てです。10月から5月ごろの期間に着る着物はこの仕立てのものです。
さらに、浴衣の衿はそのまま着られるバチ衿で仕立てられていますが、着物は広衿と言って衿を半分に折り曲げて着付ける仕立てになっています。
着る場面の違い
浴衣はもともと風呂上りに着るものでした。寝間着や部屋着が原型なので、夏祭りや散歩程度のカジュアルな外出用です。フォーマルな場所には不適当です。そして、浴衣を着てよい時期は6月から8月ごろの夏のみです。
着物は、様々な格に分かれていて、食事などのお出かけはもちろん冠婚葬祭の場面などフォーマルな場所にもTPOに合わせたものを着ます。
着付けの仕方の違い
浴衣の着付けはシンプルで、肌着の上に浴衣を着付けます。しかし着物は、肌着の上に必ず長襦袢を着てから着ます。
そして、着丈は、浴衣の場合くるぶしにかかるくらいに合わせますが、着物の着丈は特にフォーマルな格のものは床すれすれに合わせて着付けるという違いがあります。
浴衣は帯もシンプルです。着物の袋帯の半分の幅の半幅帯や子供にも使う兵児帯を合わせます。
着物では、フォーマルな場面には袋帯、ちょっとしたお出かけなどには名古屋帯を使います。
さらに、着物の着付けでは、帯の上に帯締めと帯揚げを使いますが、浴衣では、基本的には使いません。
そして、最後に履物の違いです。
浴衣では、素足に下駄が一般的ですが、着物では、足袋を履いて草履を履くという違いがあります。
着付けに使うものの違い
浴衣と着物の着付ける時の必要なものの違いはこちらです。
浴衣を着用するのに必要なもの
1.浴衣(ゆかた)
2.ウエストベルト(なければ腰ひも)
3.コーリンベルト
4.伊達締め(だてじめ)
5.半幅帯(はんはばおび)
6.浴衣用帯板(ゆかたようおびいた)
7.肌着(はだぎ)
8.タオル2~3枚
9.腰ひも2~3本
着物を着るのに必要なものリスト
1.着物(きもの)
2.袋帯(ふくろおび)
3.長襦袢(ながじゅばん)
4.帯締め(おびじめ)
5.帯揚げ(おびあげ)
6.重ね衿(かさねえり)
7.草履(ぞうり)
8.足袋(たび)
9.肌着(はだぎ)
10.衿芯(えりしん)
11.ウエストベルト
12.コーリンベルト2本
13.伊達締め2本(だてじめ)
14.前板(まえいた)
15.帯枕(おびまくら)
16.腰紐3本(こしひも)
17.フェイスタオル5本
18.補正用品(ほせいようひん)
着物を着るのに必要なものは、浴衣の時の倍のものが必要です。振袖を着付けるとなるとさらに多くのものが必要になります。
浴衣がいかに簡単に着られるかがわかりますね。
☆浴衣の着付けについてはこちら☆
一人でできちゃう浴衣の着付け総集編
浴衣の着付けと帯結びレパートリー
まとめ
いかがでしたか?
今回は、浴衣についてでした。
浴衣の原型は平安時代にあったことなど歴史について知ることで、浴衣を着る時の意識が変わってきませんか?
今年も、浴衣を着て夏のイベントを楽しんでくださいね。
☆浴衣の着付けや帯アレンジなどお役立ち情報満載☆
浴衣についてのブログはこちら
☆袴の身のこなしや当日の持ち物などお役立ち情報がいっぱい☆
卒業式関連のグログはこちら
☆振袖専門館花舎の振袖コレクションはこちらから☆
色別やジャンル別でたくさん載ってます
↓↓↓↓↓↓
https://kasya.jp/furisode/
☆花舎の前撮りインスタグラムはこちら☆

WEBでのご予約はこちら
こちらをクリック