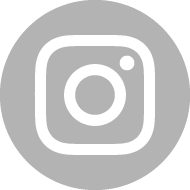振袖BLOG
振袖のお役立ち情報を発信中
【成人式】直前対策!式前日から振袖を脱いだ後のポイントをわかりやすくご紹介

成人式をお控えの皆様、ご準備はいかがですか?
いざ直前になると、前日までに何をしておくと良いか、当日に気を付けることは何か?気になってきませんか?
今回は、成人式直前に気を付けてほしいことと、振袖を着ているときに気を付けてほしいこと、振袖を脱いだ後の扱いについてご紹介します。
ぜひ、参考にしてくださいね。
☆振袖専門館花舎の振袖コレクションはこちらから☆
色別やジャンル別でたくさん載ってます
↓↓↓↓↓↓
https://kasya.jp/furisode/

Contents
前日までにしておきたいこと
成人式前日に気を付けていただきたいことは、二つあります。
まずは、よく睡眠をとること、そして、朝食を支度会場に行く前にとっておくことです。
睡眠不足や空腹状態で着付けをすると体調を崩してしまうことが多いです。
そして、お支度は着付けよりもヘアメイクから先にされることが多いと思うので、前開きの洋服を用意しておきましょう。
その他の準備は次の通りです。
ヘアのカット・カラーは一週間前までに
振袖を着るときは、ヘアスタイルも重要ですね。かわいく理想のヘアスタイルにセットしてもらうために、前髪やカラーを整えておきたいですよね。
美容師さんに成人式でしたい髪形を伝えて(具体的な画像などを見せるとわかりやすいと思います)、実現できるようにベースのスタイルを作ってもらいましょう。
万が一、思い通りのカラーなどにならなかった場合、直前だと修正ができないので、一週間前までに美容室に行っておくと安心です。
ネイルの準備もお早めに
ネイルは必ず必要なものというわけではないですが、振袖に合わせて準備される方も多くなってきましたね。振袖の雰囲気に合わせて爪の先までおしゃれをするのも楽しいですね。
ジェルネイルの場合は前日でも大丈夫ですが、余裕をもって一週間くらい前に施しておくと前日あわただしくならないのでおすすめです。
学校やアルバイトの関係で自爪にアレンジできない方もネイルチップなら当日のみでも楽しめます。
ネイルチップは当日につけますが、ネイルチップ自体の準備は前もってしておきましょう。前撮りがある方はその前に、当日だけ付ける方も早めに注文しておきましょう。
ネットで注文される場合はオーダーメイドのことが多いので、注文から届くまで2週間から一か月くらいかかる場合があります。納期をしっかり確認しておきましょう。
手荷物も前もって準備しておきましょう
バッグの中身の準備とお支度会場に行く準備をしておきましょう。
振袖用のバッグは、デリケートなので、荷物の入れすぎに注意してください。無理なく締められる程度に荷物を入れましょう。
無理やり入れると、バッグ留め具が壊れてしまいます。バッグに入れるものはできるだけコンパクトにして、厳選しましょう。
きれいな着姿を保つための身のこなし
成人式当日、着慣れない振袖で動くのは緊張するかもしれません。しかし、動き方を知っていれば何も怖いことはありません。
ここからは、振袖での身のこなしと簡単な着崩れの直し方をご紹介します。
振袖を着た時の立ち方歩き方

立つときは、つま先を揃えることを意識しましょう。足を開いて立ったり、片足に重心をかけたりするとだらしなく見えてしまうので気を付けましょう。
歩くときは、歩幅は草履一つ分くらいを目安に、いつもより小さめを意識しましょう。そして、膝を高く上げるのではなく、内股ですり足気味で歩くと裾が広がりにくく美しい姿になります。
イスに座るときの注意点
イスに座るときに気を付けていただきたいことは大きく2点です。
袖が床にすらないように上げることと、着物のお尻部分が裂けないようにすることです。

袖を上げないと、床をすってたもとが汚れてしまったり、立ち上がる時に自分で踏んでしまって脇の袖付けが破れてしまう危険があります。
座っている間、袖は合わせて、膝の上にたたんで置いておきましょう。
バッグを持っているときは、あらかじめイスの背もたれに添えるように置いておきましょう。座っているときは、帯の下に空間ができるので、物置になります。
両手が使える状態で座る準備をします。

着物の縫い目が背中の中央を通っているため、特に深く沈み込むようなソファに座るときは気を付けてください。背中心部分を持ち上げたまま座らないとお尻のところが裂けてしまうことがあります。

座る位置は、帯がイスの背にぶつからないように、前の方に浅めにしましょう。
浅めに座ると、重心が前になるので自然と姿勢が良くなって着姿が美しく見えます。せっかくの着物姿なので、姿勢も意識できるといいですね。
足を組むのはご法度です。着物の前合わせはタイトになっています。足を開いて座ると前合わせが崩れてしまうので気を付けましょう。
立ち上がるときは、裾を踏まないようにゆくっりと立ち上がります。袖は、立ち上がるまではたたんで持っておきましょう。
階段の上り下りのポイント

階段を上るときも下るときもまず、イスに座るときと同じように袖を左腕にかけて持ちます。
袖を持たずに上ると、たもとを踏んでしまって袖付けが破れてしまう場合があります。
次に、裾を踏まないようにするために、右手で着物の合わせ部分をつまんで足袋の高さくらいまで持ち上げます。
慣れない草履をはいていると足を上げづらいと思うので、ゆっくりと気を付けて上り下りしましょう。

階段の上り下りも袖や裾をケアしないと、せっかくの振袖が汚れてしまったり、破れてしまったりするので注意が必要です。
着物を着た時の簡単なお手洗いの行き方

お手洗いに行くときは、まず、袖を軽く縛ります。少しの時間なら、シワにはならないので上の方で縛ってください。

続いて裾を上げていきます。着物クリップを2つ準備します。帯の上にセットし、結んだ袖を包むようにして、着物の上前、下前の順に一枚ずつめくり、クリップで留めていきます。この時、着物の後ろ側までしっかり上がっていることを確認しましょう。長襦袢、肌着も同じように一枚ずつクリップで留め、後ろもしっかりあげます。すべて留めるとひざ丈くらいに納まるはずです。
座るときは、帯がぶつからないように気をくけてくださいね。

そして、手を洗う時も袖が濡れてしまわないように気を付けましょう。
画像のように、たもとをクリップで留めておくと安心です。
振袖を着た時の車の乗り降りの仕方

車に乗るときも、まず両袖を左腕にかけて持ちます。
次に、座席に対して後ろ向きに軽く腰掛けます。ヘアスタイルが崩れないように、前かがみの状態で頭を車内に入れます。

頭を入れたら次は、両足を軽く浮かせてお尻を軸に身体を90度回転させ、全身を車内に入れます。
乗車中は、背筋を丸くすると帯で腹部が圧迫され、苦しくなってしまうので、背筋は伸ばしておくとよいでしょう。その際、前の座席や取っ手につかまっていると帯結びをつぶすことなく綺麗な状態を保てるでしょう。
降車の際は、これまでの手順を反対から行ってください。
降りる時は特に、袖や裾を車のボディーなどにすってしまったり、踏んでしまったりしないように気を付けましょう。
袖の長い振袖で食事をするとき

食事をするときは、利き手と反対の手で袖口をおさえます。振袖はたもとが長いので、思わぬところで汚してしまいやすいです。手を伸ばすときは必ず袖口をおさえましょう。
そして、着物を汚してしまわないように、膝にハンカチなどを敷きましょう。心配な方は、衿元にハンカチを挟んで汚れを防ぎましょう。
トラブルの対処法
衿が浮いてしまったら

着物姿では、お顔周りでもある衿の美しさが重要です。
振袖の場合は、特に未婚女性の第一礼装ということもあり、衿が詰まっています。そのため、首や上半身を動かしたりしていると、衿元のバランスが崩れてくることがあります。
もし衿元が緩んでしまったら、指を伸ばしてスライドさせるようにそっとシワを衿の中に入れます。この時力を入れすぎないように気を付けましょう。衿の後ろの“ヌキ”が詰まって歪んでしまいます。
おはしょりの直し方

着物を着て、立ったり座ったりを繰り返していると、“おはしょり(帯の下から出ている折り返しの部分)”がシワになったり、めくれてしまったり、乱れてしまうことがあります。
そんな時は、おはしょりと帯の間に指を入れて左右にしごいてシワをとります。おはしょりの長さは約6cm、幅がすべて均等になるように直しましょう。
おはしょりは後ろまで続いているので、後ろにできたシワも指を入れて脇に寄せましょう。
振袖を脱いだ後の衣裳の扱い
成人式が終わって振袖を脱いだら、まずは汗を飛ばしてください。
冬でも意外と汗をかいているものです。湿ったままでしまってしまうとカビの原因になりますので、気を付けましょう。
振袖、帯、長襦袢をはじめ、小物類や着付け道具も干して乾かしましょう。心配な場合は、クリーニングに出すと安心です。
乾いたら、シワにならないようにきちんとたたんでしまっておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は成人式の直前対策と成人式後の衣裳の扱いについてでした。
ちょっとしたケアで着姿の印象や、着崩れやトラブル防止になるので今回のポイントを覚えておいてください。振袖の場合、長い袖と裾に特に気を付けていただければと思います。
思い出に残る楽しい成人式にしてください。
☆振袖専門館花舎の振袖コレクションはこちらから☆
色別やジャンル別でたくさん載ってます
↓↓↓↓↓↓
https://kasya.jp/furisode/

WEBでのご予約はこちら
こちらをクリック